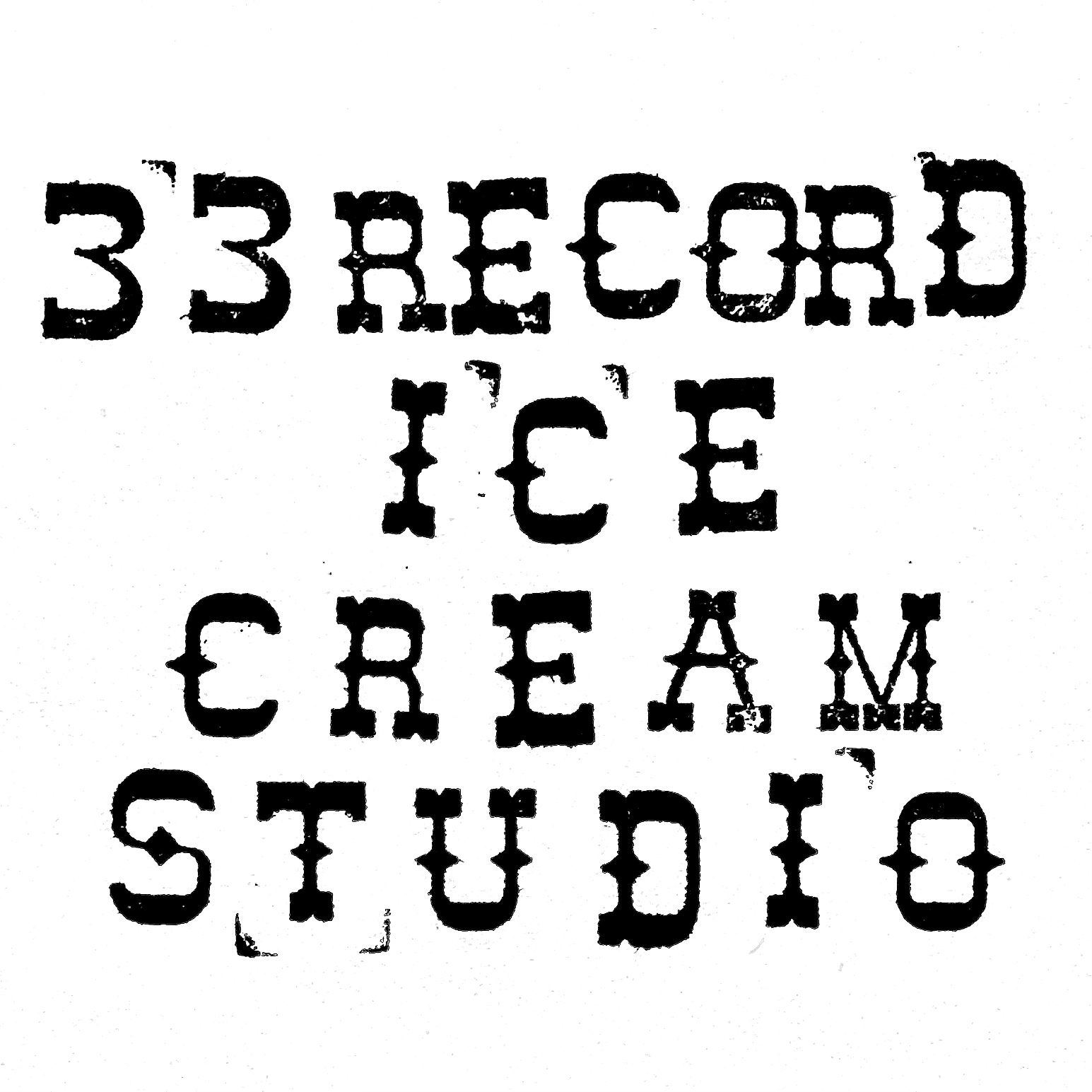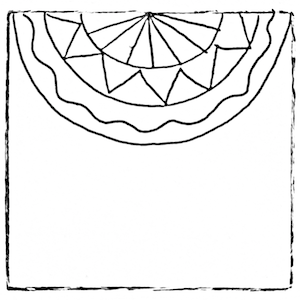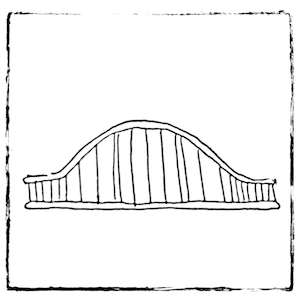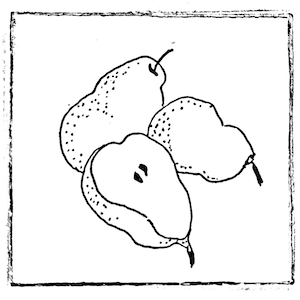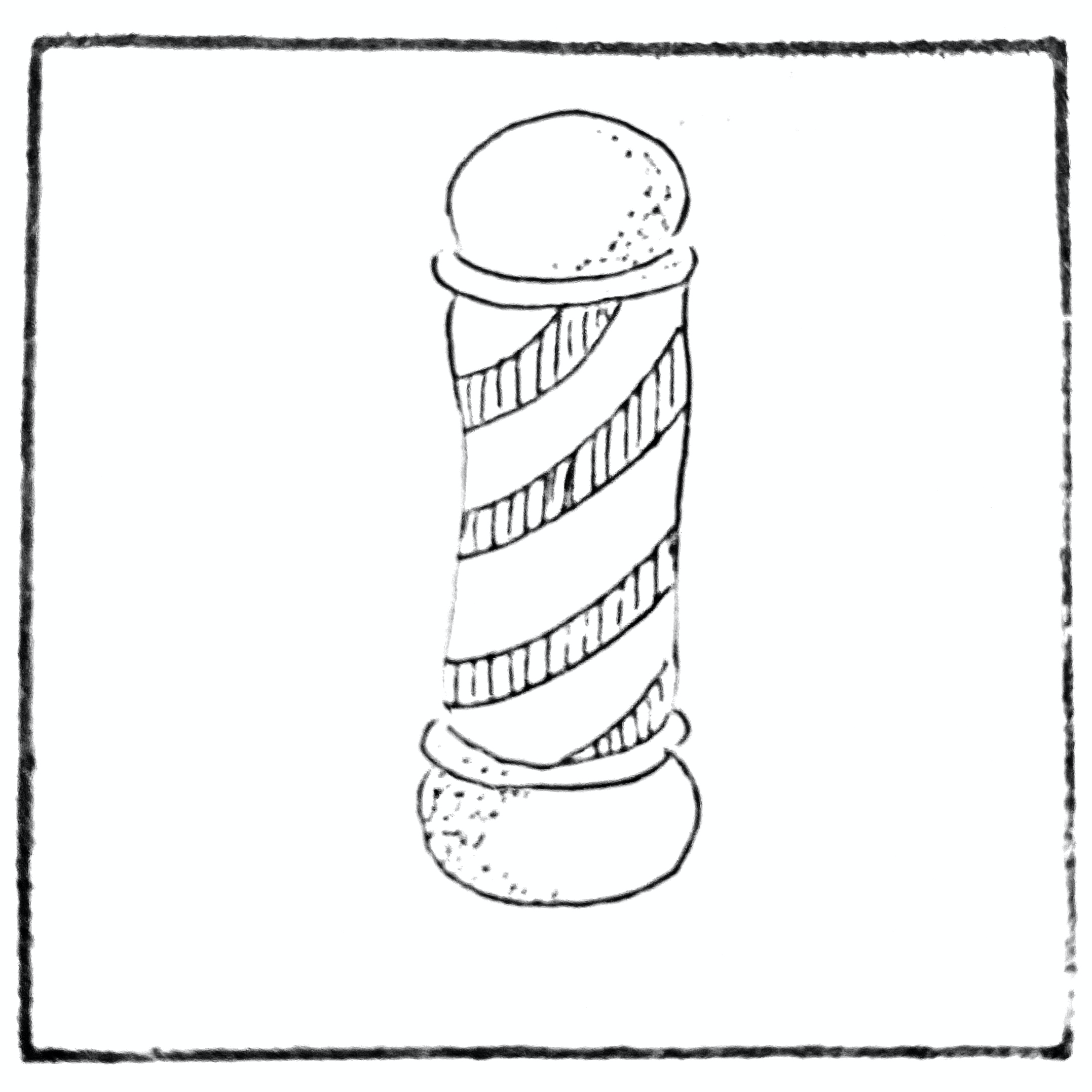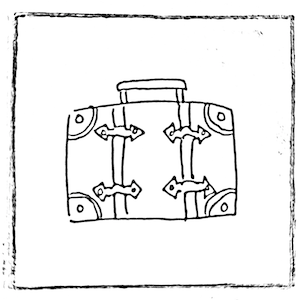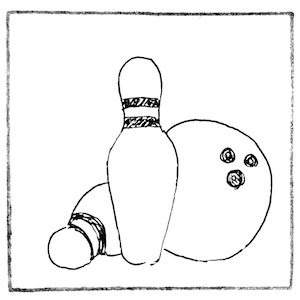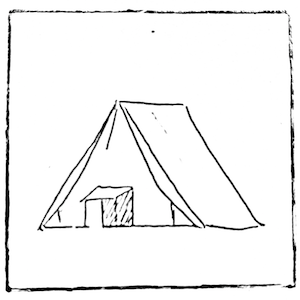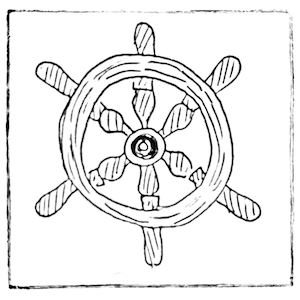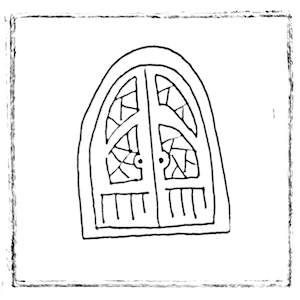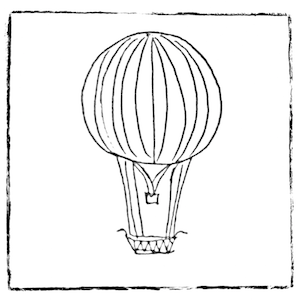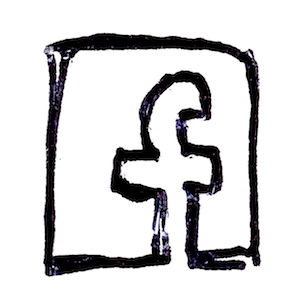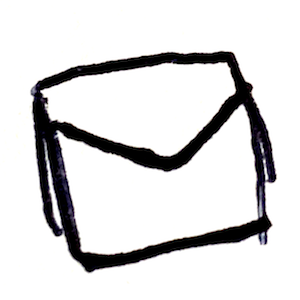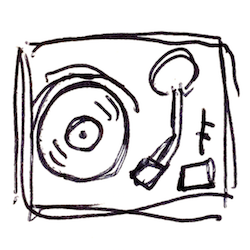THIRTY THREE RECORD
人と歴史①
Date : 2025.09.08/ Author:Yawn of sleepy
「音はわかるけれど音楽はわからない音楽人、これが一番致命的」
との言葉を聞いた
40年も前から言われていることだそうだ
今もそうなのに今の話ではない
宮沢賢治のいうところのニセ教師ってやつかな
まー沢山いますよ、知らないわからないが言えない音楽人
昔はもう少し違ったのかと思ってたから意外でした
誰かを指して言う時には批判だが
自分たちを指して言う時には自省
音楽観は大抵10代の頃の強い感化から関心を辿って拓かれていく
リスニングの拡張が初期で停滞しているままではわからないのも無理はない
探究を必要としない段階の人もいる
これを隠して語る人も多いし音楽好きでいたい故の気持ちもわからなくもないが
無知から始めるのは皆同じ
大海を知るとは、楽しくおもしろく学びの海を沖に泳げているかという問いだろう
同じものに触れたはずでも
知覚の範囲の差異によっては
感覚を分かち合うことは難しい
聞こえてきた音を「聴いてみる」、「わかりたいと思う心」から始まるのが音楽
それを置いて語るから肝心単純な話がややこしくなっている、のも昔からのようだ
謙虚さは、音作りにも出ること
むしろややこしくして「聴けないわからない」を都合よくうやむやにしている
こういったついついの手法が
お手本のひとつとして印象づくと音楽文化は乱れ加速せず小さくなります
「わかる力と喜び」よりも
「わかりやすさ」や「紹介と仕掛け」が共有の根拠となってしまうから
悪くなったのではなく、なんだ悪い癖は昔から同じだそうだよ
ーーー
流れ込んで来たのは
自分のことではないと思いたい40年と前後で、自分達のことと省みる40年と前後
勿論、こんな話と縁のない文化的生活が一番良いわけですが
責任を背負って考える人の背中を見ていたいし学びたい
日本屈指のキャリアの方達の話題としては情けないとは思った
わかった上で開示してくれた事実を受け止めたい
人の音楽もろくに聴けない人が自分の音楽をアピールして何かを期待しているとか
マルパクリ曲を真顔で発表&著作権を振りかざすとかも
例えばレンタルサービス~インターネット~サブスクの話題のように
そこらで聞くおんなじような話になるんだなあとも思いました
おんなじようなところでがんばってきた、とも言えてしまう
自省、けれども誰にとっても他人事ではないと思う
全員真剣で、実力も運もあってハッタリで仕事してるわけでもないのだから
為になる話ではあったけどなんかモヤっときたな
当事者の先輩たちの疑問や憤りが美談みたいにされていたことも
続きのストーリーにエールと期待を抱いている
誰かと誰かは向き合えているか、人と人は、人と音楽は
大小や規模を問わず
役割を担う人、言い張れる人、参考にできる人のために書いておきます