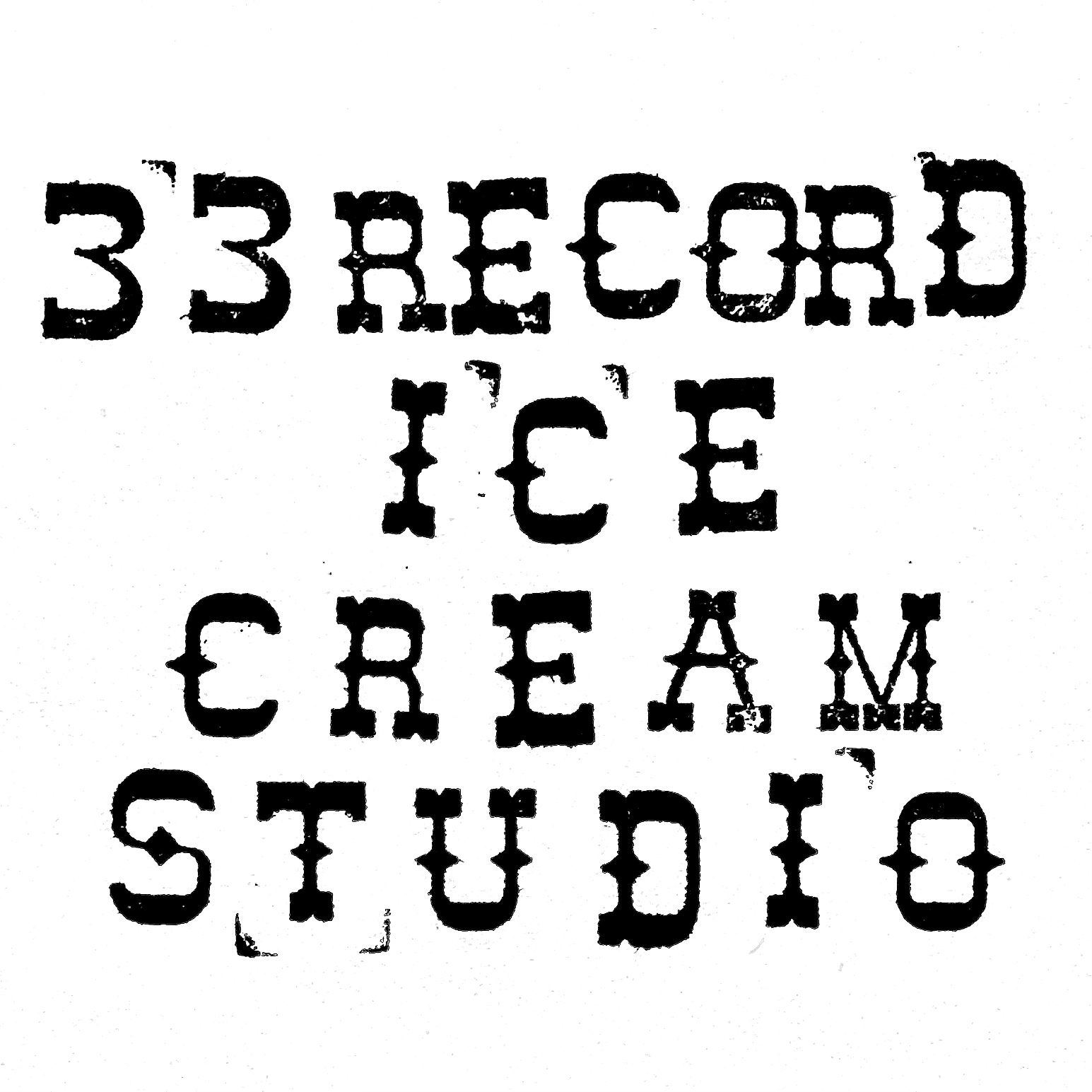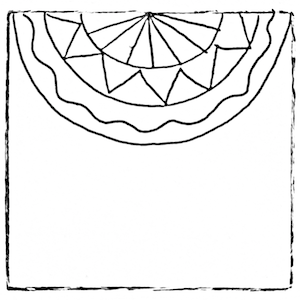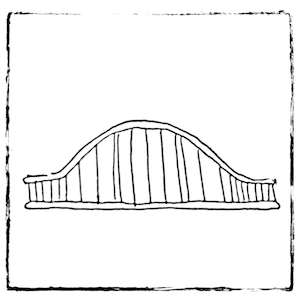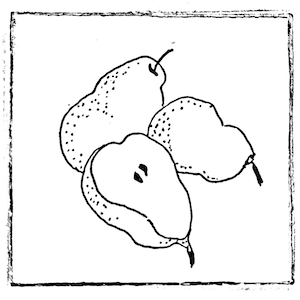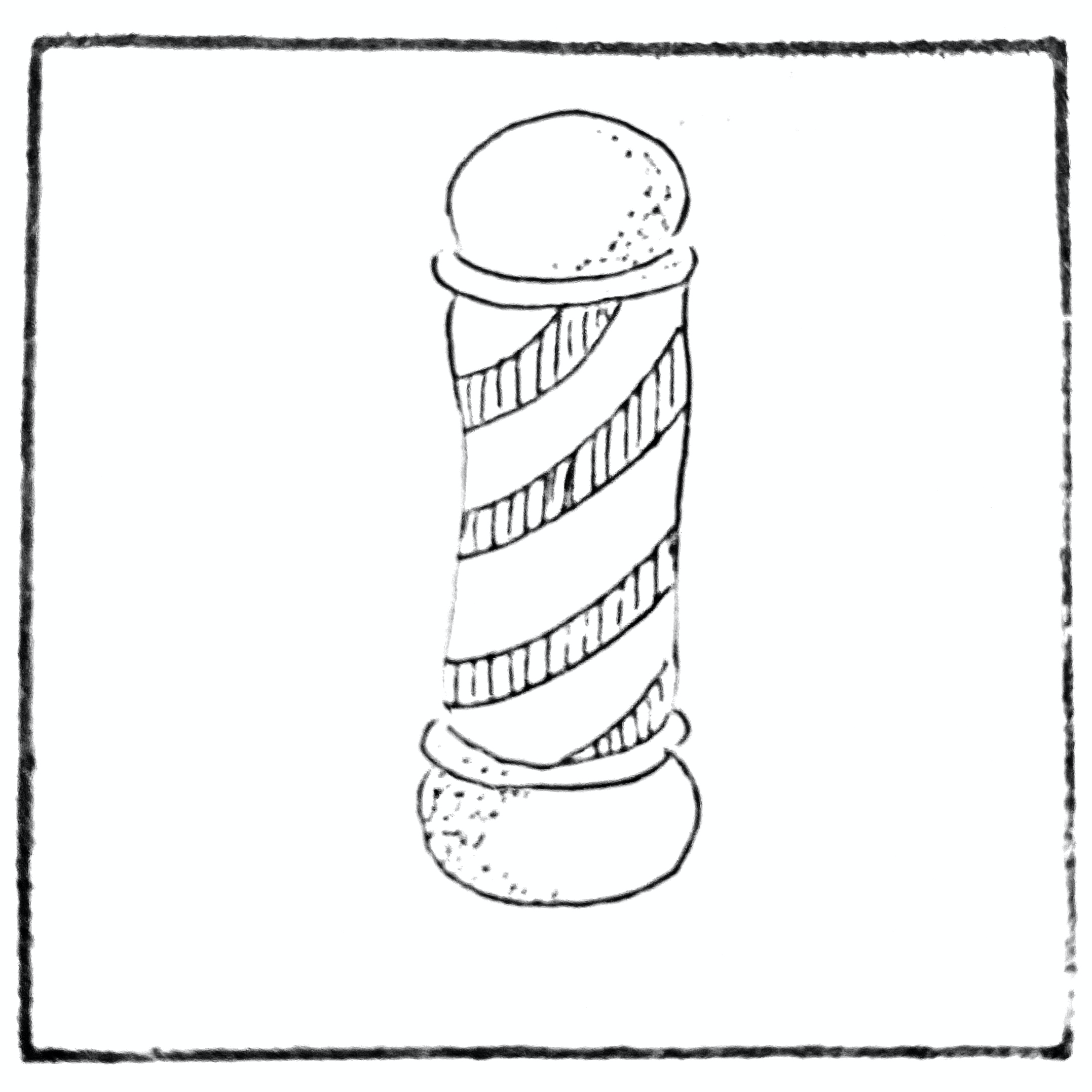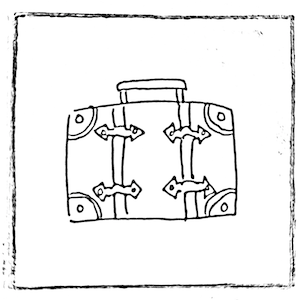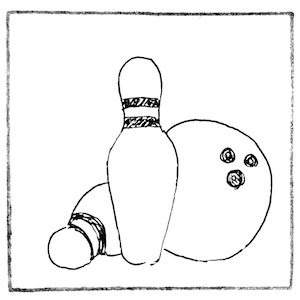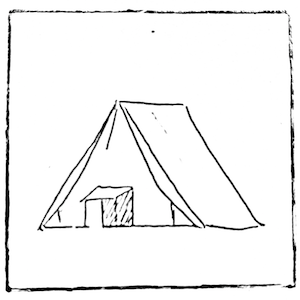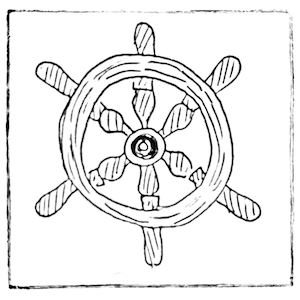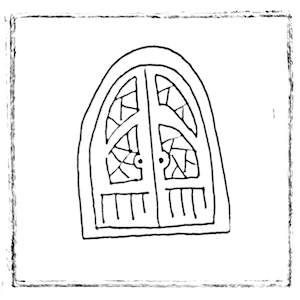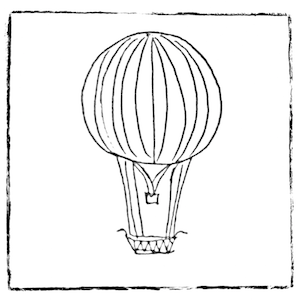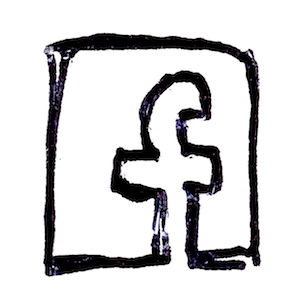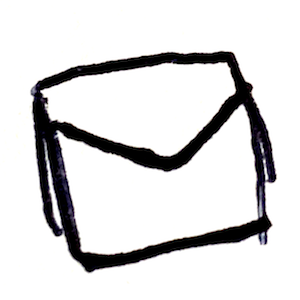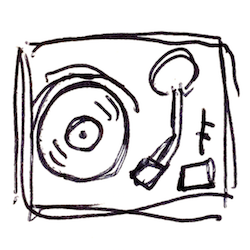THIRTY THREE RECORD
人と歴史②
Date : 2025.09.08/ Author:Yawn of sleepy
「日本のスタジオは一番きれいですね、ですが全部同じ音」
「個性があってはいけないような方向性でつくっているような感じ」
と続く言葉を聞いた
これも40年も前から言われていることだそうだ
今もそうなのに今の話ではない
まー確かにそれは事実として絶対そうなのだけど
皆が使えるようにという偏りのない配慮を兼ねつつ
無個性気味なタレント表現や演出に色をつけ華をもたせるには
周りの色を抜くのが手っ取り早いコントラストってことを狙いとして
わざとそうしてきた側面がありますから、意外でした
そうつくられた空間に疑問を持てる人もそらいるかとは思います
「場が持つ力や偶然」を「音響」と誤変換してしまう傾向は強い
これは音楽に織り込む要素を音や言語という限定範囲で認識している結果だし
楽しめるはずの沢山の要素が見えていないというもったいない事実かと思う
ある種、録音もツアーもリゾートなわけだから
そしてこれは聴いてきたお手本にもよるもの
「音の分離が、帯域が」とか
「これはどこそこの機材だエフェクターだ」とかいう声は聞こえてくるわけだから
そういうものは音楽を通して認識できている
一方で
ここで提起された「場所の力や状況」のおもしろさが織り込まれた音楽
というものに触れたり、なによりその手触りを感じられた機会
センスのお手本が少ない故に
設計上の要素としても優先度が高くにこないわけだ
そしてそもそも
一日何十万円というようなスタジオワークは経験しない人の方が多い
原音主義か加工系統かというような選択を楽しむ以前に
知らない感覚を分かち合うことは人にとってとても難しい
ましていまの時代ならプロでもなおさらだ
これらを指して一流だの、次元違いだのと
もてはやされたい人、もてはやす人もやはり本質からずれている
良い音楽を作る為には音や機材など関係ないのだと語る別の口と信念で
当事者の方達にはちゃんとひっくり返していて欲しい
今の皆もそうと知ればやるだろう
進歩のない40年なんて全世代、望むものではない
誰かを指して言う時には批判だが
経験に基づいた比較文化論、当事者間の痛烈な自省と取れば
芸術家にはあっても良いことだと思う
40年の間に、咲いた花と、咲かなかった花が確かにあって
種や土、水、光、どれかだけの話をすることは狭量といものだろう
問いは単純
「大切なことってなんだっけ
老若男女皆、忘れたり見失ったりしてないか」ってこと
ーーー
流れ込んで来たのは
自分のことではないと思いたい40年と前後で、自分達のことと省みる40年と前後
勿論、こんな話と縁のない文化的生活が一番良いわけですが
責任を背負って考える人の背中を見ていたいし学びたい
日本屈指のキャリアの方達の話題としては情けないとは思った
わかった上で開示してくれた事実を受け止めたい
人の音楽もろくに聴けない人が自分の音楽をアピールして何かを期待しているとか
マルパクリ曲を真顔で発表&著作権を振りかざすとかも
例えばレンタルサービス~インターネット~サブスクの話題のように
そこらで聞くおんなじような話になるんだなあとも思いました
おんなじようなところでがんばってきた、とも言えてしまう
自省、けれども誰にとっても他人事ではないと思う
全員真剣で、実力も運もあってハッタリで仕事してるわけでもないのだから
為になる話ではあったけどなんかモヤっときたな
当事者の先輩たちの疑問や憤りが美談みたいにされていたことも
続きのストーリーにエールと期待を抱いている
誰かと誰かは向き合えているか、人と人は、人と音楽は
大小や規模を問わず
役割を担う人、言い張れる人、参考にできる人のために書いておきます