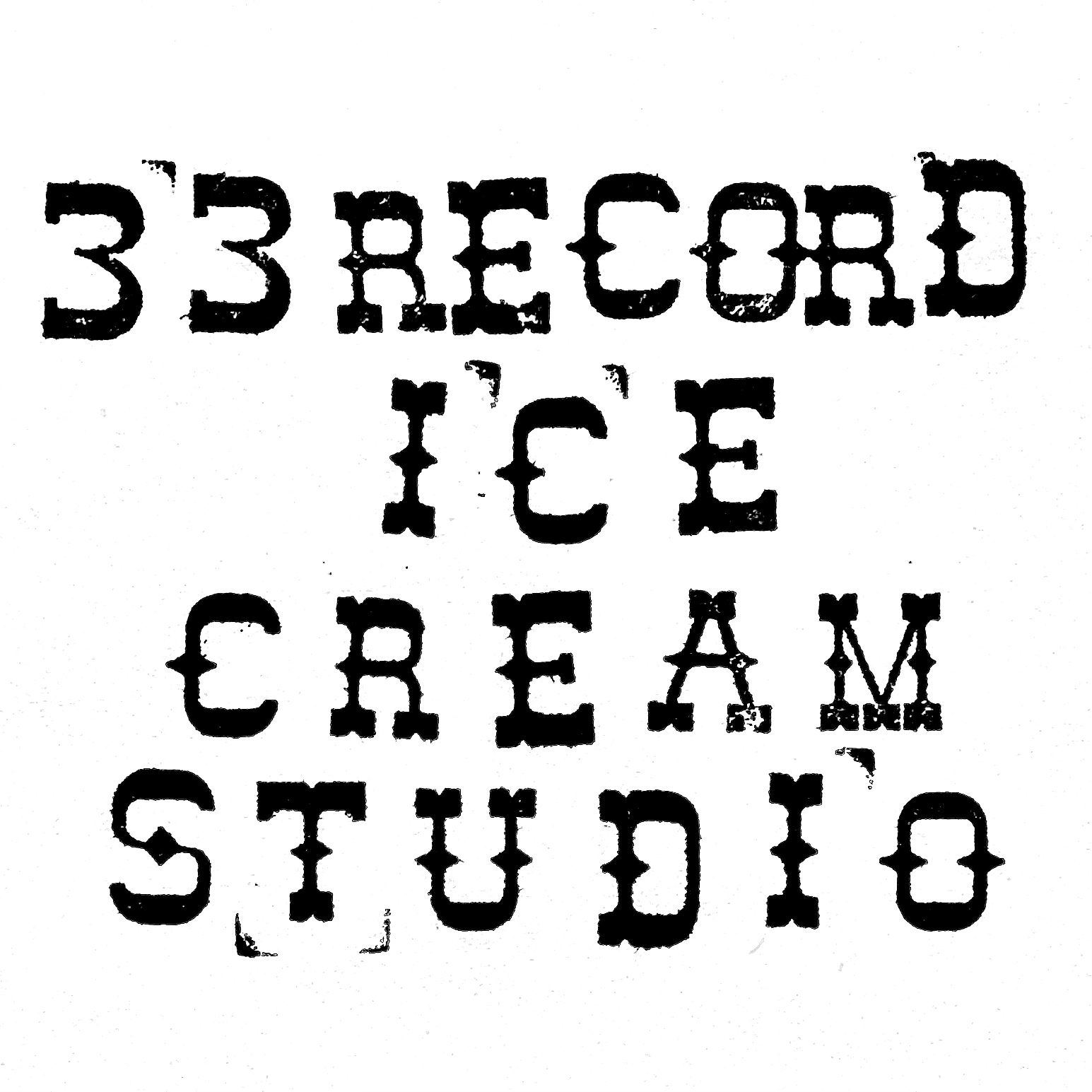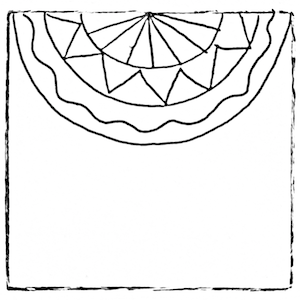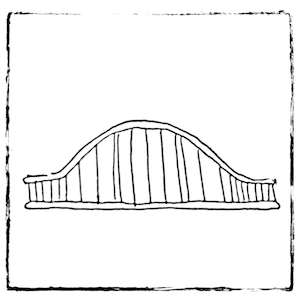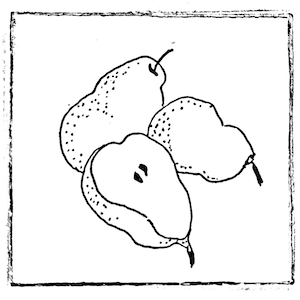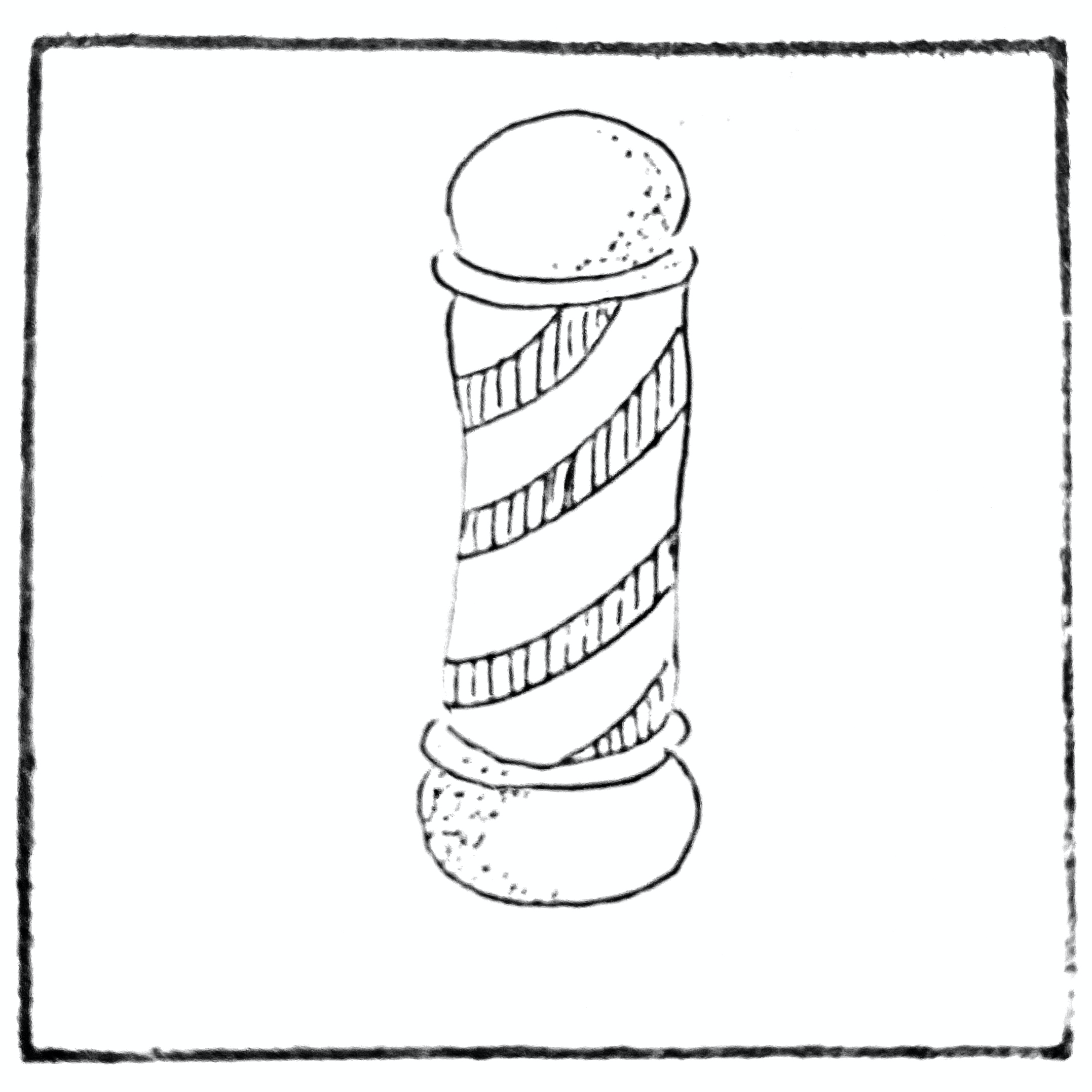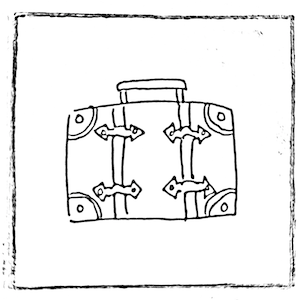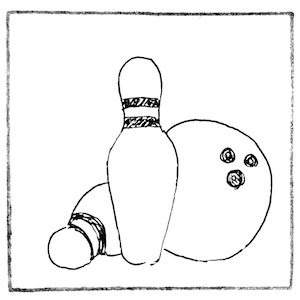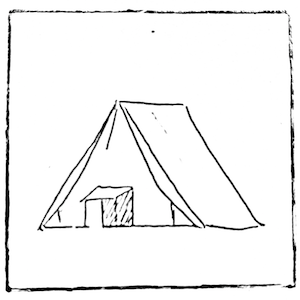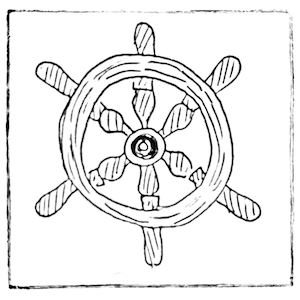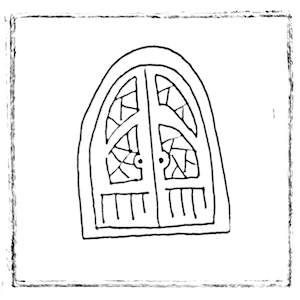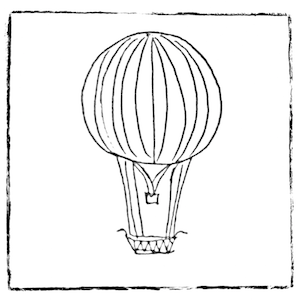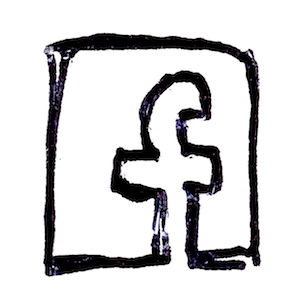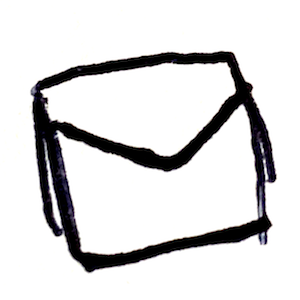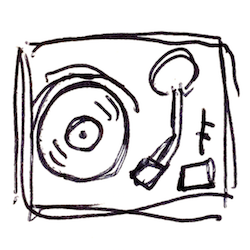THIRTY THREE RECORD
人とスタジオ
Date : 2025.09.10/ Author:Yawn of sleepy
「音楽というのは風俗を動かすなにかであったけれども、
今は風俗の後に音楽がついていってる」という言葉を聞いた
「映画音楽はやりがいがあるが、劇伴はやらない」と続く
この二つの言葉は同じ内容を指している 音楽の力とはたらきの順序の話だ
しかも40年前に感じていたことだそうで
だけどCMやらSNSをみていれば今にもなんら変わらずそのまま言えること
実際、映画監督やTVディレクターが音楽を指して「音は後で」なんてよく言うし
「音楽が場面を食っちゃうから」などと演出表現を変更する場面は幾度も見た
音楽と向き合うアーティストが、向き合う故の音楽観に基づいて
音楽の力について語れるのは本来当たり前、決して役割への無理解ではない
今なら(もしかしたら当時も)、タイアップや劇伴を喜んじゃう人が多勢のなかで
そう、音楽から始まること、その様を見たいと、やはり
ミュージシャン自身が音楽の力を知り、発揮していて欲しいと願えるかということ
「日本の音楽は子供向きにつくってますね、子供は良し悪しで買わないから」とも
「ディレクターとプロデューサーは日本では曖昧な存在」
「言葉としてはあるけれどもどう換算したらよいかがわからないのではないかな」
「事実、クレジットに名前はあるけれど、本質的な人は誰もいませんね」とも
痛烈かもしれないが事実であって飄々と、丸めこまれない位置にいるひとの
業界のトップネーム達と仕事をしながらにあるこれらの発言は音楽愛によるものだ
残念なのは「願える人」が孤立してしまうこと
チームやスタッフ、関係者、リスナー、業界の体質そのもの、多勢が今も昔も
このような提起を「どう換算したらよいかがわからない」まま
ついスルーしてしまうことだ
ひとは皆誰でも、自省があまり得意ではない
集団ともなればなおさらだ
40年前といえば、当時のスタジオでは
「音をワイワイいじるのは普通はやらないとかやってはいけないという風潮」
だったらしい
米的な原音主義が音楽録音の根幹だとは言えるが
欧的なスタジオワークによる制作感の影響下にはまだなかったのだそうだ
スタジオで音をワイワイいじるのは、つまり
録りの後の観察、瞬発的な反応/発想力を重視、楽しんでいたということ
「あるエンジニアとのコンビであれば、
どこでも絶対に良い音を作れる自信があります」
とのお話で、これは、数々のスタジオ時間でのファインプレーによるものだろう
アーティストとエンジニアの最良の到達点のひとつ、関係性だと思う
スタジオで過ごす時間を人はそれぞれどう過ごしてきたのか
何を知り、考え、なにと向き合いどう過ごすのか
ーーーー
私達にとって、この方達とのお付き合いはまだ10年には満たないくらい
有難いことに、週末や週中、テーブルに呼んでは音楽談義、制作を労ってくれる
そんな時間の中、テーブルの上
エンジニアである氏の言葉に好きなものがある
「深夜とかにスタジオをこう静かに眺めているとなんか音の匂いがするよね」